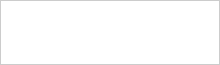評価損とは、一般に、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額をいいます。
評価損は、①技術上の評価損と②取引上の評価損に分類されます。
1.技術上の評価損
技術上の評価損とは、修理を行っても主として技術上の限界から事故車両の機能や外観に回復できない欠陥が残る場合の損害のことです。
技術上の評価損は賠償すべきであるという点にはついては、ほぼ争いはないようです。
2.取引上の評価損
取引上の評価損とは、事故歴があるという理由で当該車両の交換価値が下落する場合の損害のことです。
この取引上の評価損についての裁判例は、肯定例、否定例とも多数存在しており、明確な一定の基準を示すことは困難ですが、一般的には、①初年度登録からの期間、②走行距離、③損傷の部位(車両の機能や外観に顕在的又は潜在的な損傷が認められるか)、④車種(人気、購入時の価格、中古車市場での通常価格)等を基準に評価損が発生するか検討すべきとされています。
これまでの裁判例の傾向として、外国車又は国産人気車種で初年度から5年(走行距離で6万㎞程度)以上、国産車では3年以上(走行距離で4万㎞程度)を経過すると、評価損は認められにくい傾向にあるようです(東京地裁民事第27部[交通事故専門部]景浦裁判官の講演より[赤い本平成14年版所収])
3.評価損の算定方式
評価損の算定方式として裁判上採用されているのは、①減価方式(当該車両の事故時の時価と修理後の時価との差額を損害とする)、②時価基準方式(当該車両の事故時の時価を基準とし、その時価に対する一定割合を損害とする)、③修理費基準方式(当該車両の修理費を基準とし、その修理費に対する一定の割合を損害とする、④その他があります。
裁判例としては、③修理費基準方式を採用したものが多いようです。
私の経験でも、裁判所(裁判所)ごとに一定の基準が設けられているようで、裁判の席上で裁判官より「当裁判所としては、初年度当登録から●年以内の車両について、修理代の●割を評価損として認めております」と言われたことが何度かありました。
したがって、裁判において、評価損を認めてもらうためには、車種・初年度登録年度・走行距離・損傷の部位等を具体的に証明できる資料を提出する必要がありますが、通常は、修理代見積書にこれらの事項が記載されています。
- 投稿タグ
- 評価損