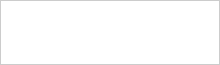死亡事故の場合、被害者の遺族が請求できる項目は以下のとおりです。
①葬儀関係費
②逸失利益
③慰謝料
④弁護士費用(訴訟を提起した場合)
なお、即死ではなく、治療後に死亡した場合には、当然、治療関係費や入通院慰謝料等を別途請求できることができます。
1 葬儀関係費
葬儀関係費は、自賠責保険で請求する場合には、定額で60万円ですが、いわゆる「赤い本」の基準(裁判基準)では、150万円とされています。
墓石建立費や仏壇購入費、永代供養料などは、個別に判断されます。
2 逸失利益
逸失利益とは、被害者が生きていれば得られたはずのお金(消極損害といわれます)。将来得られたはずのお金を計算し、その金額を将来ではなく請求時に一時金として受け取ることになりますから、いわゆる「中間利息」が控除されます。
また、生きていれば当然生活費がかかったはずなのに、死亡したことにより生活費の支払いがなくなったわけですから、将来、生活費として支出したであろう金額(割合)も控除されることになります。これを「生活費控除」といいます。
以上を前提に、死亡の場合の逸失利益の計算式は次のとおりです。
年収 × 就労可能年数に対するライプニッツ係数 × (1-生活費控除率)
(1) 年収
有職者(働いている人)については、事故前年の年収を基準にします。
若年労働者(概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり、全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則とされています。
無職者(18歳未満を含む)は、男女別全年齢平均賃金で計算するのが原則です。
(2) 就労可能年数に対するライプニッツ係数
就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされています。したがって、18歳以上であれば、事故時までの年齢を差し引いた年数に対するライプニッツ係数で計算します。例えば、30歳で死亡した場合には、67歳-30歳=37年のライプニッツ係数で計算します。
高齢者で、67歳を過ぎても働いている場合には、その後何年間働く蓋然性があるかで判断し、また年金をもらっている場合には、その年金額も考慮します。
(3) 生活費控除率
被害者が男性の場合には、生活費控除率は50%とされるのが通常です。
ただし、一家の大黒柱で、被扶養者がいる場合には、その人数により、30%~40%とされます。
被害者が女性の場合には、主婦、独身者、幼児かを問わず、30%程度で算定されるのが通常です。
3 慰謝料
死亡事故の慰謝料については、「赤い本」の基準(裁判基準)では、次のようにされています。
(1) 一家の支柱 2,800万円
(2) 母親、配偶者 2,400万円
(3) その他 2,000~2,200万円
「その他」とは、独身の男女、子ども、幼児等のことです。
近親者が固有の慰謝料を請求する場合には、これが減額され、それぞれの近親者等の固有の慰謝料に割り振られたり調整が図られることがあります。
4 弁護士費用
死亡事故に限りませんが、訴訟を提起して判決になった場合には、認容額(賠償額)の10%程度を相当因果関係のある損害として、損害賠償額に加算されるのが通常です。